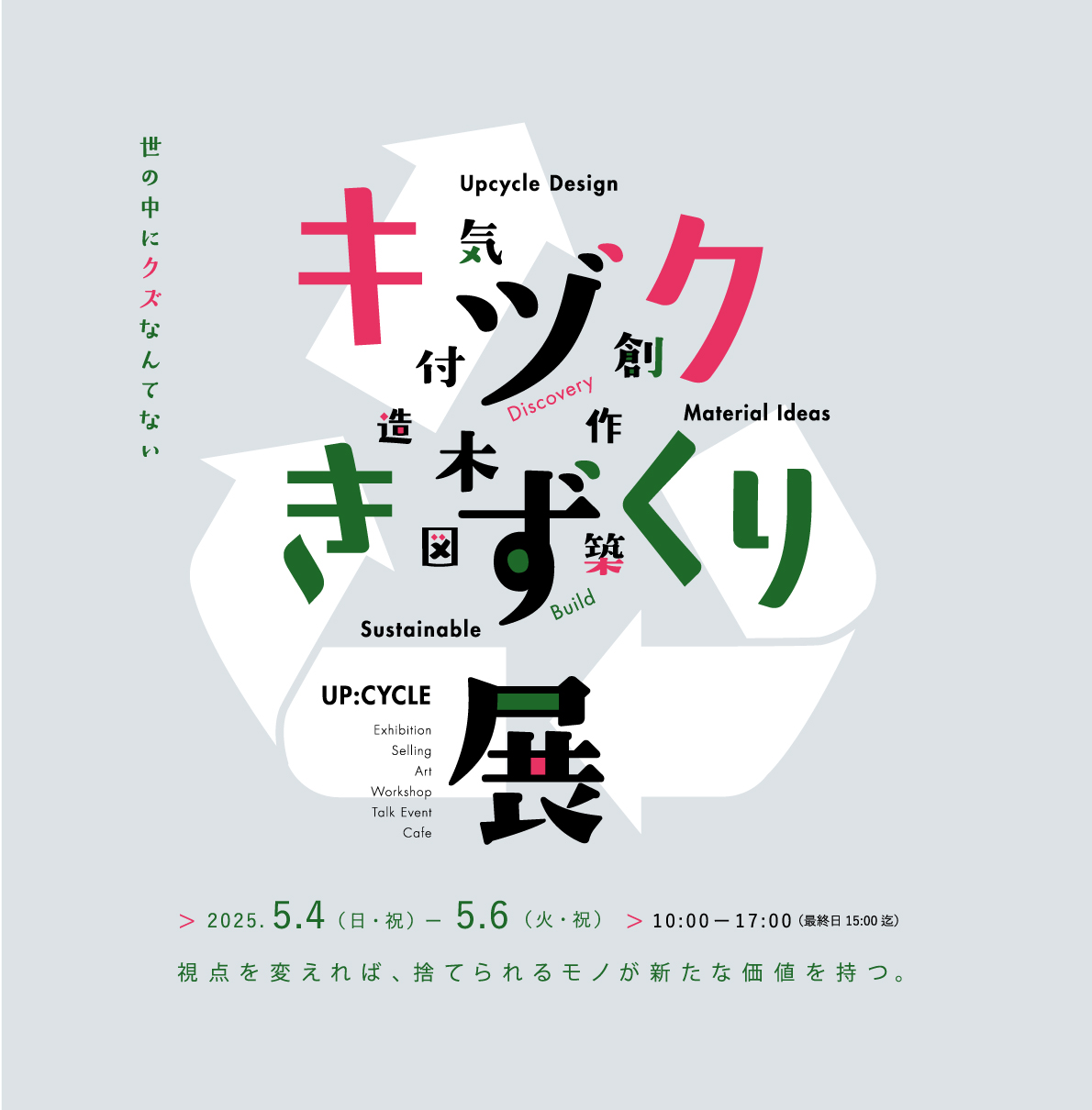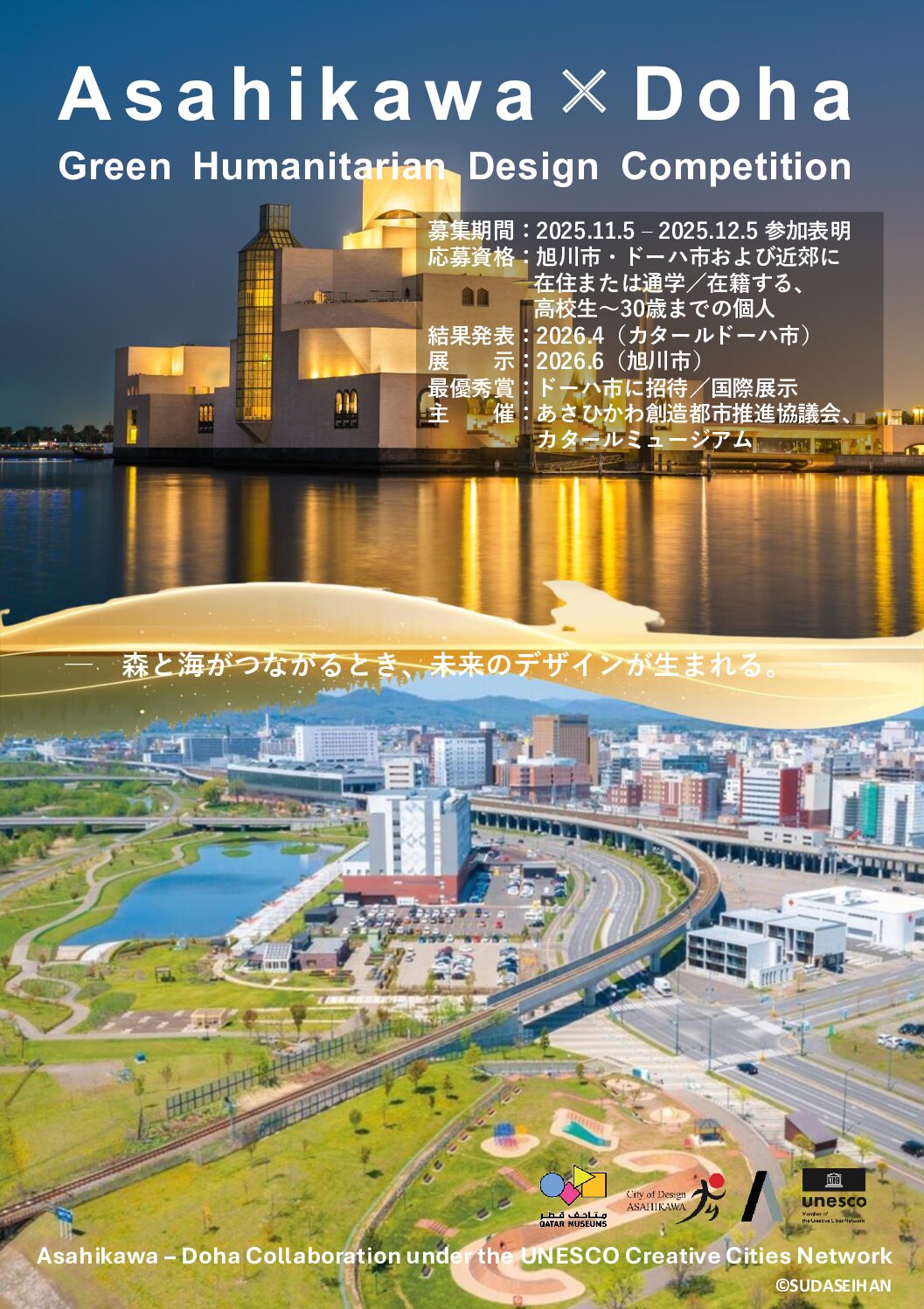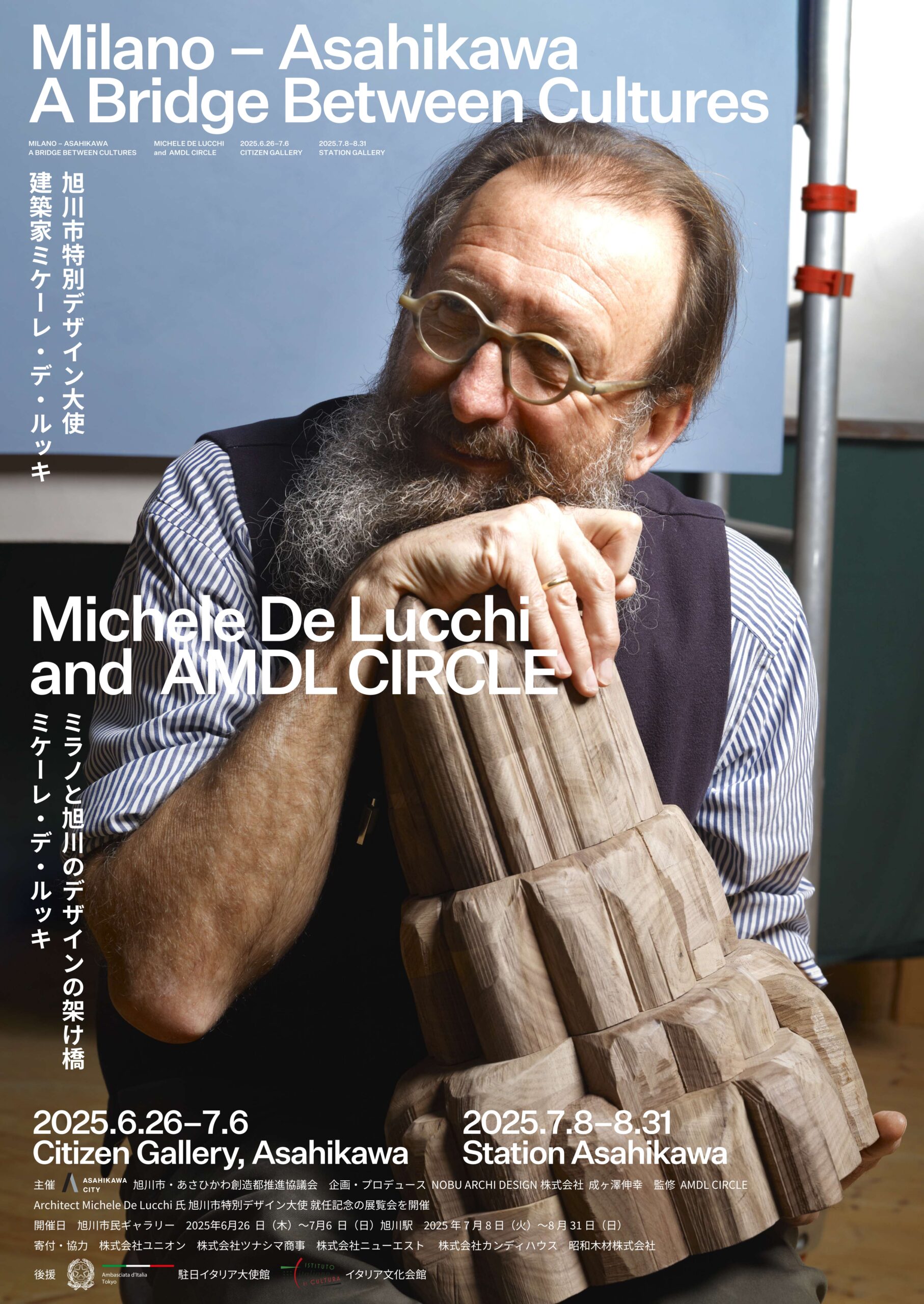問いが変われば、未来が変わる— コンセプトのつくりかた、育てかた
1.開催日:2025年9月19日(金)18:00–20:00
会 場:デザインギャラリー(旭川市宮下通11丁目 蔵囲夢)
主 催:あさひかわ創造都市推進協議会
講 師:細田 高広 氏
(TBWA\HAKUHODO 取締役/コンセプトクリエイター/『コンセプトの教科書』著者)
2.参加者数:47名
3.内 容
(1) コンセプトとは何か —— 「新しい意味」の発明
- コンセプトとは「新しい意味」を与える行為である
- 単なるアイデア・ネーミングではなく、“誰にとってどんな価値があるか”を明確にするもの
- 言葉の背後には
「これは何か」「なぜ必要か」「誰に意味があるか」
という問いが存在し、その質が未来を決める
(2) 送り手目線から受け手目線へ
3.事例を用いながら、
「スペックの説明」から「顧客が得る価値の提示」へ の重要性が語られました。
コンセプトとは“意思決定を束ねる意味の設計図”である。
(3) 意味が価値を生む
- キャンドル:照明ではなく「暗がりを楽しむ」「香りを楽しむ」体験価値
(4) 問いの変換(リフレーミング)
さまざまな角度から問いを変える実例が紹介されました。
- 物理 → 心理:空港の荷物問題=「待ち体験の改善」
- 名詞 → 動詞:マグカップ=「水を運ぶという行為」から再設計
- 利己 → 利他:新幹線清掃TESSEI=「効率的に掃除」 → 「おもてなし」
- その他:NASA宇宙ペン、危険運転抑止策など多数
(5) 4つのC(4コマ構造)で設計する
- Customer:顧客のインサイト(葛藤)
- Competitor:競合の手抜かり
- Company:自社の強み
- Concept:提供する意味
「困りごと → 未充足 → 自分たちが応える → 意味の提示」の流れが強いコンセプトを生む。
(6) インサイトは“葛藤”に潜む
- 外食チェーンのサラダ失敗:
顧客は“ヘルシー”と言いながら実際はボリュームを選ぶ - 男性美容市場:
「必要」×「相談しにくい」という矛盾が潜在需要に
(7) 価値の分解(Fact→Merit→Benefit)
同じ機能でも、対象の違いで“意味”は変わることを複数事例で解説。
(8) 言語化の型
- 二語の圧縮(例:「1000曲×ポケット」「Third×Place」)
- 変革法、メタファー法、反転法、スライド法 など
実戦的な技法が多数紹介されました。
4.会場ワーク
テーマ:「ダイニングテーブルを“動詞”で再定義する」
参加者からは、
「学ぶ」「遊ぶ」「飾る」「避難する」「語る」など多様な動詞が挙がり、
“名詞から連想する固定概念をはずす”ことで、発想が大きく広がる体験となりました。
5.閉会のことば
渡辺会長からは、
- ユネスコ創造都市加盟から5年を「再スタートの節目」と捉えたい
- 市民に親しまれるデザイン活動へと広げていきたい
- 今日学んだ「問いを変える思考」を、市民と共有して旭川の未来をともにつくりたい
との総括が述べられました。
6.まとめ
本セミナーは、コンセプトを「問い」や「意味」として捉え直す重要性を学び、
“問いが変われば未来が変わる”という実感を持ち帰る場 となりました。