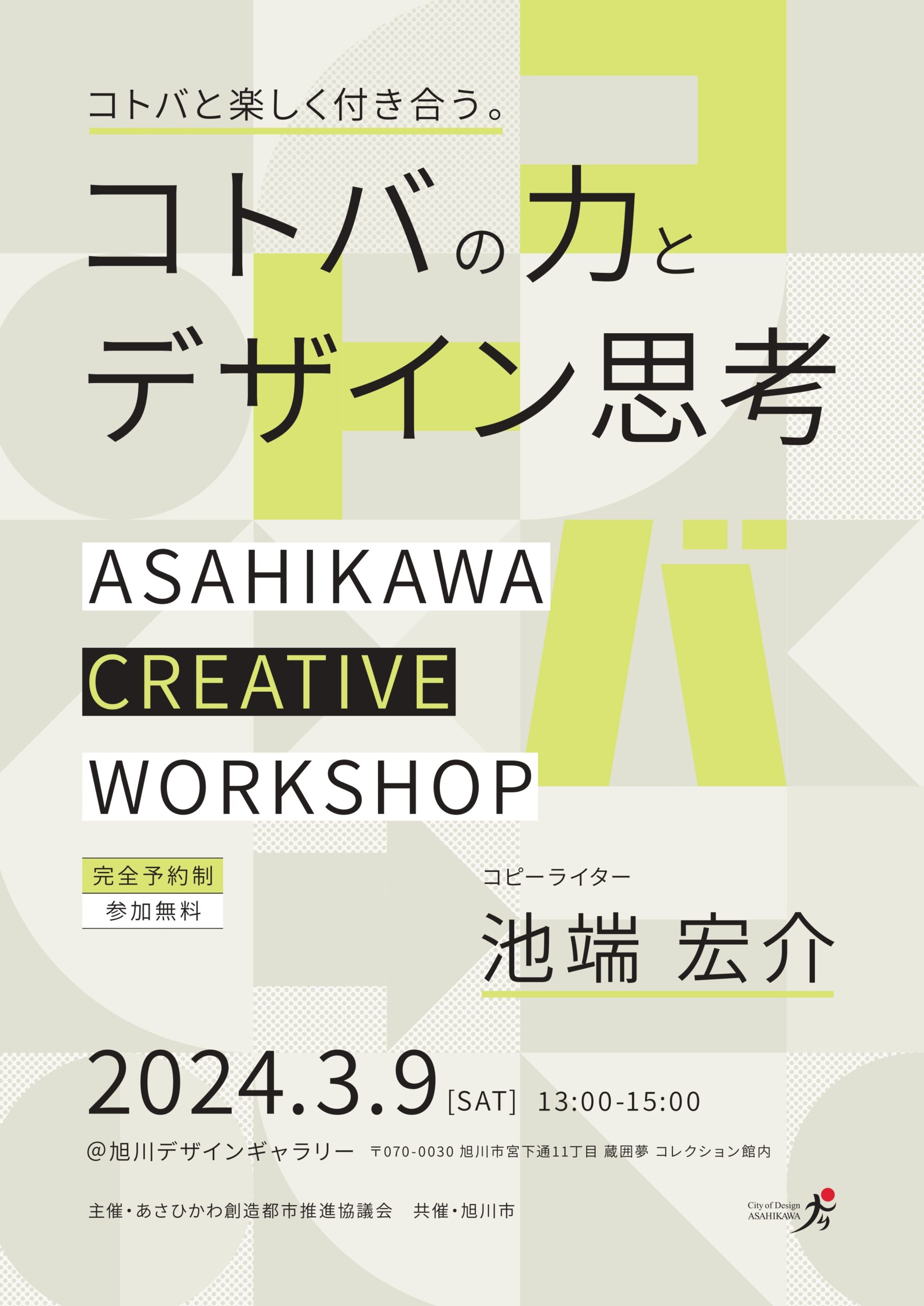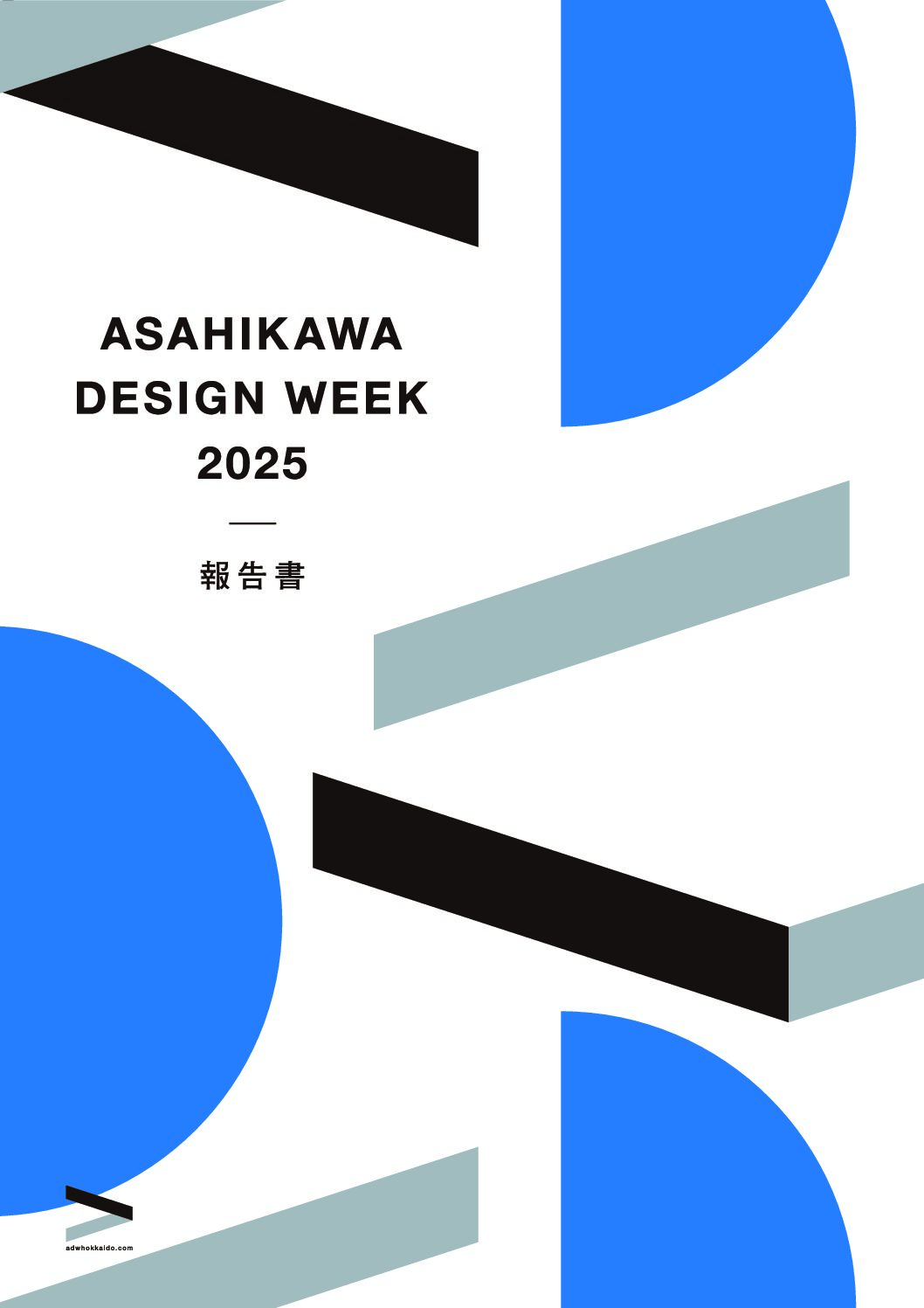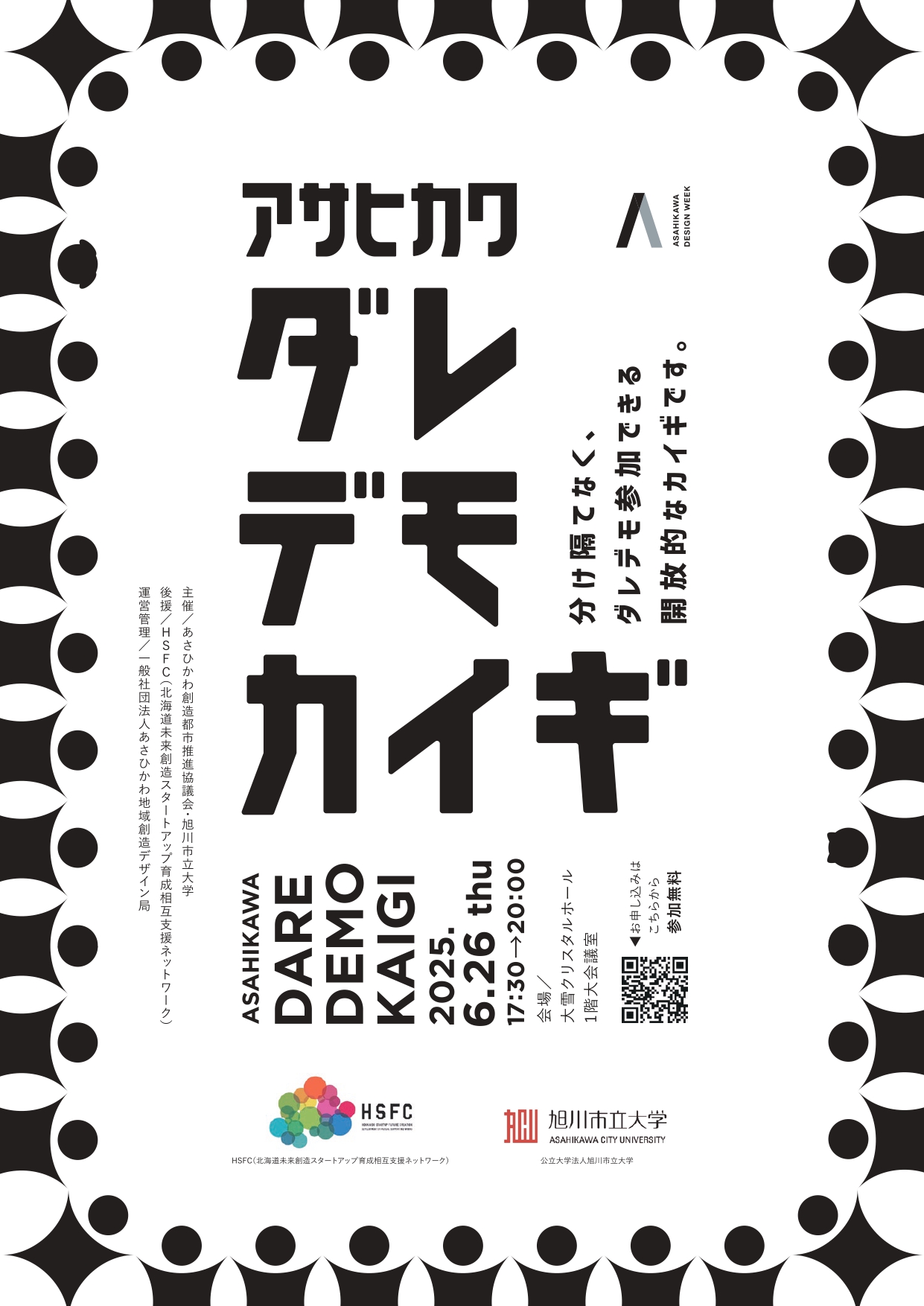「生成AIとまちづくり」
33名が参加し、AIが拓く“地域未来の可能性”を学ぶ
あさひかわ創造都市推進協議会では、令和7年3月10日(月)、
デザインギャラリーにて、
デザイン・クリエイティブセミナー「生成AIとまちづくり」 を開催しました。
講師には、糸島サイエンス・ヴィレッジ構想を牽引する
平野友康 氏(イトシマ株式会社/テレポート株式会社 代表) を迎え、
生成AIが地域づくりにどのようなインパクトをもたらすのか、
糸島での先進的な取り組みを交えて共有いただきました。
当日は、企業・行政職員・学生・クリエイターなど 33名 が参加し、
AIを使ったワークのデモンストレーションや議論を通じて、
“これからのまちづくり”の新しい視点を得る場となりました。
● セミナーの目的
今回のセミナーでは、
インターネット普及以上の社会変革をもたらすと言われる 生成AI を、
“地域づくりにどう活用できるか” という視点で学びました。
特に、
- AIを使った 発想の拡張
- まちづくりの 合意形成の補助
- “未来のまち”を住民と共に 描く力
に焦点を当て、糸島での実践事例を紹介しました。
■ 1. 糸島サイエンス・ヴィレッジ構想とは
平野氏が中心となって推進するプロジェクト
「糸島サイエンス・ヴィレッジ構想」 は、
九州大学の広大なキャンパス隣接地にある空き地(山、畑、林など)を、
“科学と実験の村” として再編集する取り組みです。
● プロジェクトの特色
- 「誰もやらないなら自分がやる」と、
平野氏が “無償でいいのでやらせてください” と名乗り出て急進展 - 糸島市・九州大学と協定を結び、
民間主導のまちづくりモデル として現在開発が進行中 - 地域の子ども、漁業者、農家、大学研究者などが
“一気通貫で連携できる場=フルスタック環境” を構築
● 糸島版フルスタックの魅力
- 「研究したい」「試したい」と思った瞬間に、すぐに地域の専門家に相談できる
- 農業・漁業・教育が半径数キロ圏内でつながっており、
実証実験が極めてやりやすい土壌 - AI・ロボティクス・生物資源研究などのテストフィールドとしても魅力が高い
平野氏いわく、
「地域に“実験できる土壌”があることがイノベーションの起点になる」とのこと。
■ 2. 市民参加型ワークショップ:想像力 × AI の掛け算
糸島では、市民同士で未来を語り合う 参加型ワークショップ を多数開催しています。
● 「いつでも飲める糸島」
雑談から出たユーモラスなアイデア
「糸島を“いつでも飲める街”にしたい!」
から、AIを使って瞬時に具現化。
- 自動運転バス × バーカウンター
- 海沿いを移動しながら楽しめるモビリティ
- 山道仕様の“移動式飲食スペース”
一見冗談のようでも、AIで画像化すると
移動サービス × 観光 × 自動運転
という新しい産業案に変化していくプロセスが紹介されました。
ワークを通じ、参加者同士が
「未来の街」を 視覚的に共有 できたことで、
議論が一気に深まりました。
● 生成AIの役割
- これまで“頭の中だけ”で終わっていたアイデアが
数秒で画像・資料・ルート案まで可視化 - リアルタイムでCG化されるため、
住民同士で バックキャスト(未来から逆算する議論) が容易 - 発想のスピードが上がることで、
「議論が止まらない」状態が生まれるのが最大の効果
■ 3. AI活用で広がる可能性と課題
● AIがもたらす主な変化
- アイデア創出の加速
- 思考の外部化(AIを“思考エンジン”として使う)
- 専門領域の参入障壁の低減
→ プログラミングやデザインなどが“AIでまず作ってみる”時代へ
地方にとっては、
「時間も予算も限られている」という弱点を補うツールになり得ると説明されました。
● 注意すべき点
- AIの情報は誤った内容を含む可能性があるため、人による検証が必須
- 住民合意や予算化など、社会的プロセスはAIだけでは成立しない
- 地域の“物語”や“文化”を無視すると、技術先行の街づくりになってしまう
平野氏は
「街はコンテンツであり、人が主役。AIはその加速装置」
と強調されました。
■ 4. 具体例:LRT導入調査のリアルタイムAIリサーチ
セミナー中には、
「もし旭川市にLRT(路面電車)を導入したら?」という
仮想シミュレーションをAIで実演。
- 国内外の事例をAIが数十秒で収集
- 目的、メリット・デメリット、費用試算、都市構造への影響を即レポート化
- 従来なら数ヶ月かかる作業の“概要”を短時間で把握可能に
その後、住民ワークショップで議論を深めれば、
計画の実現性をスピーディに判断できる
という可能性が共有されました。
■ 5. AI時代の人材育成と地域経営
● “全員が詳しくなくていい”
地域に数名、
AIを使いこなせる人材がいれば、
アイデアを次々と具現化できる。
重要なのは
得意分野を持つ人同士がゆるやかにつながる“人的ネットワーク”。
● 教育機関との連携
平野氏は、学校現場でもAI教育を展開し、
小中高生と一緒に“未来の糸島”を考える授業を実施。
こうした教育連携は、
地域全体でAIリテラシーを底上げする仕組み
としても成果を上げています。
● 街づくりは“コンテンツづくり”へ
建物や施設に投資するだけでなく、
どんな体験・文化・営みを生み出すかが重要。
AIは、そのコンテンツづくりを
加速し、支え、広げる道具 として位置づけられます。
■ 6. まとめ:AI×まちづくりが切り拓く新しい未来
セミナーを通じて浮かび上がったポイント:
- 住民の自由な発想を、AIが“即、形にする”時代へ
- 予算・時間の壁が小さくなり、地方でも大胆な挑戦が可能に
- 人間は“創造性”に集中し、AIが作業をサポートする関係に
- 最終判断・合意形成・文化の継承は、人にしかできない役割
■ 最後に
糸島での実践は、旭川にとって大きな示唆となる内容でした。
平野氏が語った
「AIは加速装置。街はコンテンツ。主役は人。」
という言葉が象徴するように、
これからのまちづくりは、大きな投資よりも、
“人の想像力”をどう引き出すか が鍵になります。
地方だからこそ、
小回りをきかせながらAIを活用し、
独自の文化や魅力を形にしていくチャンスがあることを実感できるセミナーでした。